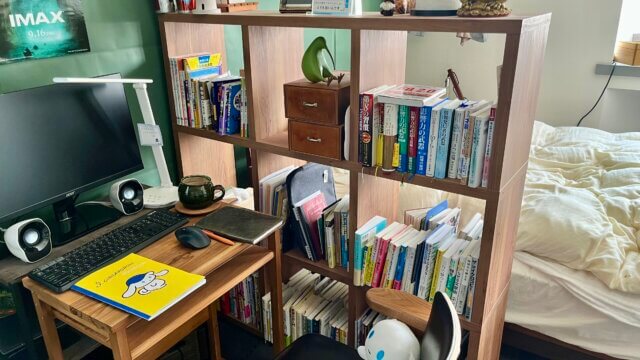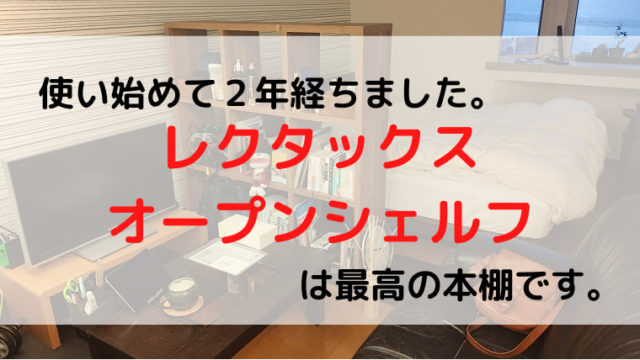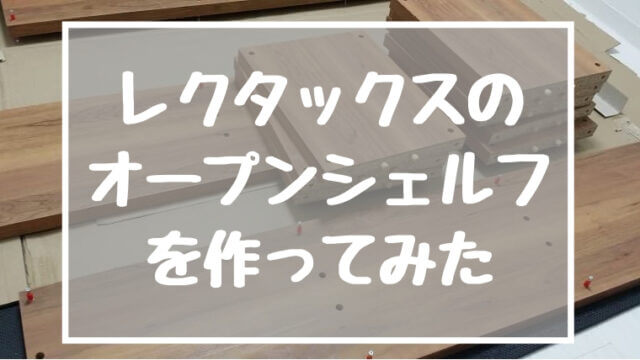【即効性あり】仕事のストレスで眠れない悩みを解消する7つの習慣
「今日も仕事のストレスでなかなか眠れなかった…」
「布団に入っても、明日の仕事のことが頭から離れない…」
そんな悩みを抱えていませんか?
仕事のストレスは、自律神経のバランスを乱し、睡眠に悪影響を及ぼします。さらに、スマホやパソコンといったデジタルデバイスの影響も、知らず知らずのうちに眠りを妨げているかもしれません。
この記事では、ストレスで眠れない悩みを解消する7つの習慣をご紹介します。副交感神経を活性化させ、心と体をリラックスさせることで、ぐっすり眠れる状態を目指しましょう。
- ストレスで眠れなくなる原因とメカニズム
- 今夜からできる具体的な対策
- 習慣化して眠りの質を安定させる方法
仕事のストレスで眠れない原因とは?すぐに実践できる対処法

ストレスと睡眠の関係
現代社会において、仕事や人間関係のストレスは避けられないものです。実際、厚生労働省の調査にでも、約5人に1人が「睡眠に関する問題」を抱えていると言われています。
ストレスが溜まると、自律神経のバランスが乱れ、眠りにくくなる原因となります。
自律神経とは体の自動調節機能のことです。
交感神経と副交感神経という相反する機能の2種類に分類され、これらが状況や臓器に応じて優位に働くことでバランスをとっています。
交感神経:興奮・攻撃的(覚醒・集中・緊張)
副交感神経:休息・リラックス・生理的(睡眠や排泄)
例:獲物を追っている最中に排泄はしない。敵に囲まれているときに眠ったりしない。等
ストレスホルモンと睡眠の悪循環
ストレスを感じると、体は「コルチゾール」や「アドレナリン」といったホルモンを分泌します。
これらのホルモンは交感神経を優位にし、緊急時に「戦うか逃げるか」という反応を助けるものです。
しかし、ストレスが長引いてホルモンの分泌が続くと、交感神経が優位な状態が続き、心拍数や血圧が高いままになります。
これでは、眠りにつくための「リラックス状態」になれません。
また、コルチゾールは夜遅くまで分泌されていると、眠りが浅くなる原因にもなります。
朝起きても疲れが取れず、日中もぼんやりしてしまい、さらにストレスが溜まるという悪循環に陥りがちです。
そのため、自律神経をうまくコントロールしてバランスをとれるようにしてあげる必要があります。
ストレスが脳に与える影響は睡眠だけじゃないんです。
ストレスにより記憶力や集中力の低下が気になる方はこちらの記事もどうぞ

デジタルデバイスが眠りを妨げる理由
寝る前にスマホでSNSを見たり、ニュースをチェックしたりしていませんか?
実は、眠れなくなる原因はブルーライトよりも、スマホでの情報収集による「心理的な興奮」にあります。
SNSでの情報収集やメールチェックは、気づかないうちに脳を活性化させ、心が落ち着きにくくなります。
また、通知音やメッセージの着信が睡眠中に鳴ることで、眠りが妨げられてしまうこともあります。
- 寝る1時間前からはSNSやニュースアプリのチェックを控える
- 通知音はオフにし、メッセージの着信を気にしない時間を作る
- スマホは手の届かない場所に置く
寝る前はスマホを手放し、読書や軽いストレッチなど、心が落ち着く習慣に切り替えるのがおすすめです。
副交感神経を活性化!眠れない悩みを解消する7つの習慣

では、ストレスで眠れない悩みを解消するにはどうすればいいのでしょうか。カギは副交感神経にありました。
副交感神経を活性化して眠りやすくするために身につけたい7つの習慣を紹介します。
副交感神経がしっかり働かせることができるようになると、リラックスできる時間が増え、毎日をより穏やかに過ごせるようになります。
意識するだけでも変化が出るので、今日の夜からできそうなものにトライしてみましょう!
- 寝る前のデジタルデバイスを控える
- 「考えごとタイム」で悩みを紙に書き出して整理する
- 効果的なコミュニケーションで人間関係のストレスを減らす
- 深い呼吸法で副交感神経を整える
- 瞑想やヨガで心と体をリラックスさせる
- バランスの良い食事と水分補給で体の内側から整える
- ぬるめの入浴とアロマで自然な眠気を促す
副交感神経とは?眠りとの関係を解説
先述した通り、私たちの体は自律神経によってバランスを保っています。
自律神経は、活動時に働く「交感神経」と、リラックス時に働く「副交感神経」の2つがあり、副交感神経が優位だと、心拍数が下がり、血圧も安定。
体がリラックスモードに切り替わり、自然と眠りに入りやすくなります。
しかし、ストレスが続くと交感神経が優位になり、体は緊張状態のまま。寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりする原因になります。
そこで重要なのが、日常の中で「副交感神経を活性化する習慣」を取り入れること。これにより、リラックスしやすい体を作り、ぐっすり眠れる環境が整います。
習慣①:スマホやPCを控えて、眠りに集中する
寝る直前までスマホを見ていると、情報に引っ張られて考えが止まらず、眠りに入りにくくなります。さらに、SNSの投稿やニュースを見て、無意識に心が緊張してしまうことも。
- 寝る1時間前にはスマホを置き、静かに過ごす時間を作る
- 通知はオフにし、翌朝までチェックしない
- どうしてもスマホを使う場合は、リラックスできる音楽を聴くなど内容に注意する
「ついスマホを触ってしまう…」という方は、まずは寝る30分前だけでもスマホを控えることから始めてみましょう。それだけでも、スムーズに眠りに入れるようになります。
習慣②:「考えごとタイム」で思考を整理する
人間関係や仕事の悩みは、つい寝る前に考えてしまいがち。でも、夜は脳が疲れていて、建設的な考えが浮かびにくい時間帯です。
そこでおすすめなのが、就寝の1〜2時間前に「考えごとタイム」を設けること。この時間に、その日あった出来事や悩みを紙に書き出し、頭の中を整理します。
- 寝る前に悩みを紙に書き出し、頭の中をスッキリさせる
- 解決策は「日中に考える」と決めておく
- 悩みが浮かんできたら「明日考える」と区切りをつける
夜に無理に答えを出そうとすると、考えが深まりすぎて逆効果。「今は考えず、明日考えよう」と区切りをつけることが大切です。
習慣③:効果的なコミュニケーションでストレスを減らす
人間関係のストレスは、睡眠に大きな影響を与えます。特に、職場でのストレスは、就寝時にまで引きずりがちです。
そこで役立つのが「Iメッセージ」での伝え方。これは、「あなたは〜」と相手を責めるのではなく、「私は〜と感じる」と自分の気持ちを伝える方法です。
- NG:「あなたはいつも締め切りを守らない」
- OK:「締め切りが守られないと、私はスケジュール調整に困ってしまいます」
この方法なら、相手の反発を避けつつ、自分の気持ちを素直に伝えることができます。日々のコミュニケーションの積み重ねが、ストレスを減らし、眠りやすい心の状態を作ることにつながります。
習慣④:深い呼吸法でリラックス

深い呼吸は、副交感神経を活性化させ、心と体をリラックスさせる効果があります。
- 4-7-8呼吸法:4秒かけて鼻から吸い、7秒止め、8秒かけて口からゆっくり吐く
- この呼吸法を、寝る前に5回ほど繰り返す
呼吸は、無意識に浅くなりがち。でも、意識的に深い呼吸をするだけで、気持ちがグッと落ち着き、寝つきが良くなります。
習慣⑤:瞑想とヨガで心と体を落ち着かせる
瞑想やヨガも、副交感神経を働かせる習慣として効果的です。
- 瞑想:目を閉じて呼吸に集中。雑念が浮かんだら、ただ流して受け止める。
- ヨガ:「子どものポーズ」や「足上げのポーズ」など、リラックス効果の高いものがおすすめ。
寝る前の5分でも良いので、リラックスする習慣を作ることで、スムーズに眠りに入れるようになります。
大人に身につけてほしいスキルNo.1
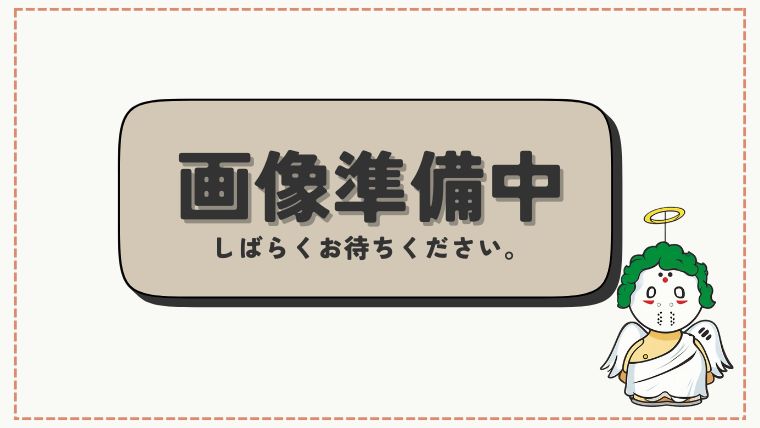
習慣⑥:食事と水分で体の内側から整える
体の内側から整えることも、良い眠りにつながります。特に、食事と水分補給は、副交感神経の働きを助け、リラックス状態を作るために大切です。
- トリプトファン(大豆製品、卵、ナッツ)
→ 睡眠ホルモン「メラトニン」の材料となり、自然な眠りを促します。 - マグネシウム(アーモンド、バナナ、ほうれん草)
→ 神経の働きをサポートし、心身の緊張を和らげます。 - ビタミンB群(豚肉、玄米、レバー)
→ 自律神経のバランスを整え、ストレス耐性を高めます。
夕食は、脂っこいものや消化に悪いものは避け、体に優しい食材を選ぶのがポイントです。
- 寝る30分前にコップ1杯の水を飲む(冷たい水ではなく、常温か白湯がおすすめ)
- カフェインやアルコールは就寝3時間前までに控える
- トイレが気になる場合は、飲みすぎに注意する
水分補給は睡眠の質にも影響します。寝る前に体を温めるように意識すると、自然とリラックスしやすくなります。
食べ物や飲み物でストレスを軽減できる?
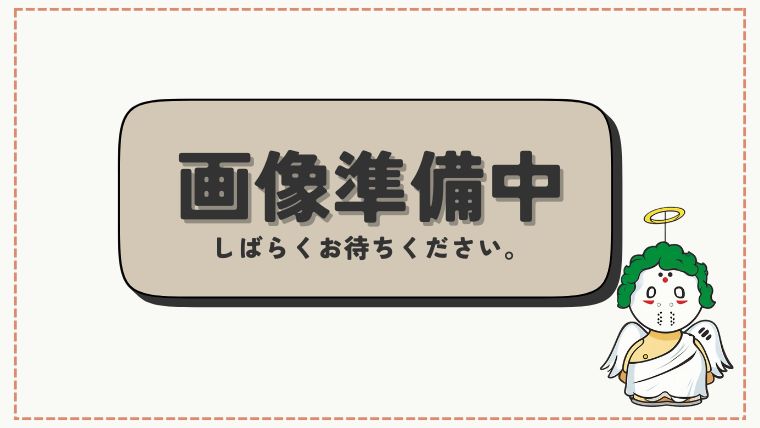
習慣⑦:ぬるめの入浴とアロマでリラックス
寝る前の入浴は、体温をコントロールして自然な眠りを促す習慣の一つです。
- お湯の温度は38〜40度のぬるめで、15〜20分ほどゆっくり浸かる
- 入浴後に体温が下がるタイミングで眠気が訪れやすい
- リラックス効果のあるラベンダーやカモミールのアロマオイルを使うと、さらに効果的
入浴は就寝の1〜2時間前が理想です。お風呂に入って体温が上がった後、自然に下がっていく流れで眠気が促されます。
さらに、アロマの香りは副交感神経の働きを助けてくれます。湯船にアロマオイルを数滴垂らすだけでも、ふわっと心地よい香りに包まれ、リラックスできます。
アロマのように睡眠の質を上げるのを助けてくれるアイテムもあります
睡眠の質にもこだわるなら、こちらの記事を読んで睡眠環境の見直しから
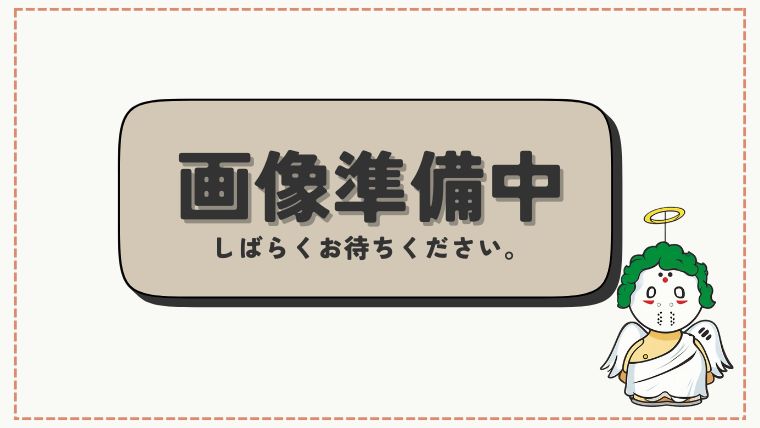
3. まとめ:ストレスに負けない睡眠習慣でぐっすり眠ろう
仕事のストレスや人間関係の悩みで眠れないと、心も体も疲れてしまいます。でも、日常の中で少しずつリラックス習慣を取り入れることで、眠れない悩みは解消していくはずです。
- 寝る前のデジタルデバイスを控える
- 「考えごとタイム」で悩みを紙に書き出して整理する
- 効果的なコミュニケーションで人間関係のストレスを減らす
- 深い呼吸法で副交感神経を整える
- 瞑想やヨガで心と体をリラックスさせる
- バランスの良い食事と水分補給で体の内側から整える
- ぬるめの入浴とアロマで自然な眠気を促す
どれも難しいものではありません。まずは「これならできそう」と思えるものから1つだけ取り入れてみることが大切です。
ストレスに負けず、毎日ぐっすり眠れるようになれば、仕事のパフォーマンスも上がり、人間関係も少しずつスムーズになっていくはず。
今日から、無理のない範囲で少しずつ実践してみてください。
4. よくある質問(FAQ)
A. 2週間以上、睡眠の問題が続いている場合や、日中の仕事に支障をきたしている場合は、専門の医療機関を受診することをおすすめします。睡眠専門医や心療内科など、専門家による適切な診断とアドバイスが効果的です。
A. 睡眠薬は、医師の処方と指導のもとで使用することが重要です。自己判断での使用は避け、まずは生活習慣の改善や自然な方法を試してみましょう。それでも改善が難しい場合は、医師に相談するのが安心です。
A. 平日と休日の睡眠時間に90分以上の差があると「ソーシャルジェットラグ」と呼ばれる状態に陥り、体調不良や日中のパフォーマンス低下の原因になります。できるだけ、平日と休日で就寝・起床時間を揃えることを心がけましょう。
A. 睡眠の傾向を知る目安としては役立ちますが、医療機器ほどの精度はありません。数値に一喜一憂せず、自分の体調や気分を重視して睡眠の質を見極めるようにしましょう。